 インタビュー
インタビュー
文武両道の進学校での不登校。病んでいく姿を見て、優等生だった息子を諦め、精神を壊すくらいなら学歴を捨てようと決心をしました。
 インタビュー
インタビュー 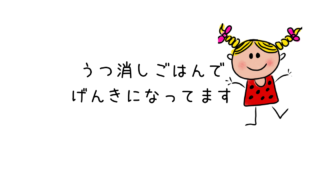 コラム
コラム  メール相談
メール相談  ライン友達
ライン友達  コラム
コラム  インタビュー
インタビュー  コラム
コラム 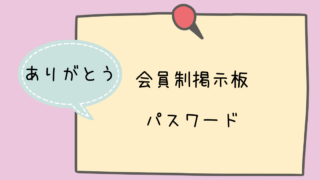 ライン友達
ライン友達  メール相談
メール相談  コラム
コラム  メール相談
メール相談  コラム
コラム  コラム
コラム 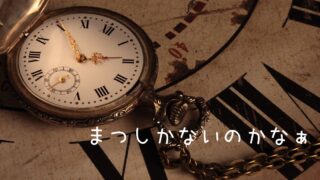 メール相談
メール相談  メール相談
メール相談  コラム
コラム  メルマガ
メルマガ  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム 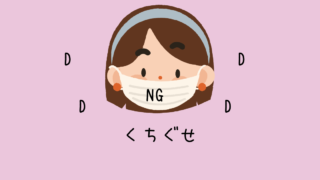 コラム
コラム  コラム
コラム 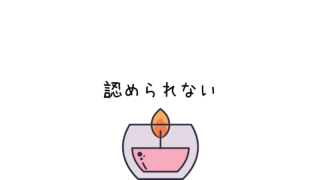 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム