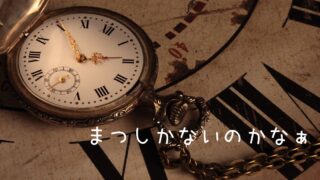 メール相談
メール相談
高2男子。学校も部活も楽しいと言っていた矢先の不登校。復学も通信制も前向きには難しそう。青春時代を支える母として明るい心持ちになりたいです。
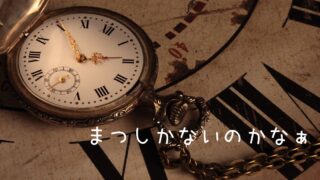 メール相談
メール相談  メール相談
メール相談  コラム
コラム  メール相談
メール相談  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム 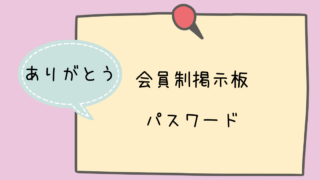 ライン友達
ライン友達  メール相談
メール相談  メルマガ
メルマガ  インタビュー
インタビュー  コラム
コラム  メール相談
メール相談 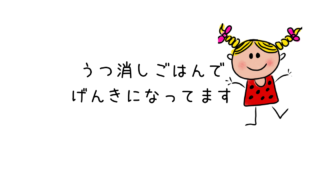 コラム
コラム  コラム
コラム  インタビュー
インタビュー  コラム
コラム  ライン友達
ライン友達  コラム
コラム 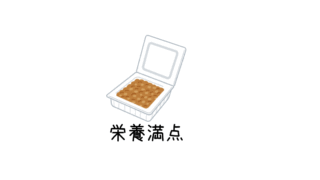 商品紹介
商品紹介  コラム
コラム 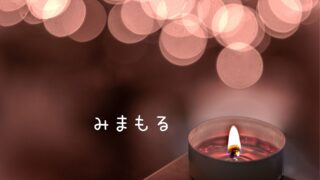 コラム
コラム  コラム
コラム 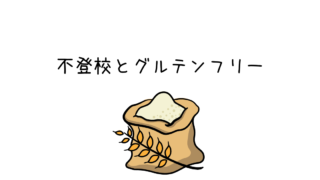 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム